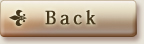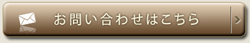夏の花 返り咲け
早朝の、まだアスファルトが焼けていない時間にカメラ担いで、近所を一周撮影散歩。散歩というのは不思議なもので、ただ歩くだけで全身が活性化し思考が整ってゆくのがわかります。
きっとそれだけ運動不足なのでしょう。徒歩移動が当たり前だった江戸時代では、旅人はいち日に8里から10里(32〜40km)歩くのが普通だったそうで、登山の経験上、一里(4km)がだいたい1時間かかりますから、お伊勢参りや、坂本龍馬のように江戸と京都を行ったり来たりする場合、毎日8時間から10時間歩いていたことになります。それができる体力と気力を普通に有していたわけです。

道路とブロック塀との5センチほどの隙間にしぶとく生息している芙蓉の木。
毎年、夏から秋まで清らかな花色を楽しませてくれます。
ところが今年は咲き始めて五日ほどで花が落ち、蕾もつかなくなりました。
異様なほどの暑さと陽射しで、さすがに弱ってしまったのでしょう。
しかし、雨が降り、気温がもう少し下がったら、たぶん返り咲いてくれるはず。
気温や水不足の苦難に遭った時、自ら葉を落としたり花を控える者は復活するのです。
がんばれがんばれ。
道端の花にエールを送る朝 雨台風の襲来望む。
電車通勤の方はきっと5千歩以上歩くでしょうし、立ち仕事をしている人なら1万歩を超えることでしょう。田舎の母は家事と畑と曽孫の世話で毎日2万歩近くになったそうで、「歩くことが大事だよ」と医者から渡された万歩計を、アホらしくなって使わなくなったと言っていました。

さてぼくはといえば、十代後半から二十代に越後の山を登りまくり、歩くのが大好きだったはずが、携帯の歩数計は千歩に満たない日がほとんどです。現場仕事(庭木の剪定や測量作業)の日でもそんなに動き回るわけではないので、せいぜい5千歩止まり。終日設計に集中した日はひどいもので、2百〜3百歩くらいで、それが何日も続いたりするわけですから、体力が落ちるはずです。

歩こ歩こ。着替えを用意して、早朝散歩を1時間以上まで延ばすことにします。コースはご近所ではなく里山がいいかな。
ひとつアイデアがあって、それはカメラのレンズを愛用の望遠ズームから、これまでほとんど使っていなかった標準単焦点レンズにすること。人の視野に近い画角で、立ったりしゃがんだり、近づいたり離れたりしながら風景を切り取るという昔ながらの撮影スタイルが、いくらかでも筋力復活になるでしょうし、感覚が、撮影に夢中だった二十歳頃にワープできることも期待しながら。