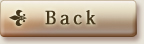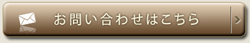設計打ち合わせの段階で庭木を選ぶ場面があります。当方の提案としては適材適所、その場所にその木を植えることの意味と意義をお伝えしつつ、しかし最終決定はお客様の好みで。「一度植えたら家族みたいに、親密で長い付き合いになりますから、よく考えて選んでくださいね」と話します。ぼくのその言葉が重めに伝わったに人は、検索したり近所の庭を覗き見しながら、樹種による成長の違いや花や果実の特徴などを勉強し、中には迷いに迷った末に、藤沢にある植木の畑(業者向けの販売店)にお連れして現物を見ながらの庭木選び、ということも。しかしまあ多くの場合は、木のことはよくわからないからお薦めを植えてください、となります。
風の歌を聴け 擬人化
擬人化のすゝめ
対象に自己を投影することは、
幼い時には誰でも持っていた思考回路です。
人を、物を、出来事を丸ごと好きになる感性を無くしたくない。
うまく生きられない人の特徴は、周囲が全て敵であると思っていること。
敵なんてどこにもいなくて、
全員が味方なんですけどねえ。
ぼくは頭が子供のままで止まっているせいか、
会う人会う人が愛おしくい思えて。
孫が遊びに来ると、庭の石ころを拾っては宝物にしています。
あれも擬人化。石とお話をしていますからね。
健やかですなあ〜。




実はこのプロセスで大事なのは、どの木を選ぶかではなく、その人が庭木を擬人化する発想を持てるかどうかにありあす。犬好きは犬を単なる犬とは思っておらず、猫好きは猫を、ヘビ好きはヘビを、連れ合い子供と同等の家族と認識して暮らしているわけで、庭において植物がそういう存在になるのだという思考に至ってほしい、という願いからのことなのです。しかし、そんな概念的なことをお話ししても迷惑がられるのがオチなので、「庭木とは長い付き合いになりますから」という言い方で、軽くこちらの世界へ、ウェルカム・トゥー・マイ・ワールドと誘っているのです。




この擬人化によって対象の価値が倍増します。それは『物』から『事』への変化です。植物を物だと思っている人は手入れにかかるコストを算出しますが、擬人化ができた人は、家族の成長、あるいはそこに投影した自分の成長が楽しみになりますので、お世話は大きなコストを費やしてでも行いたい日々の楽しみになる。犬と同じです。犬だって、相当コストがかかるもので、ぼくよりも高価な食事をしているし、トイレシートや天然素材のおやつや、散歩にかかる時間をお金に換算したら結構な額になります。こないだなんて戯れに犬用のシャンプーを使ったら、女房から「そんなもったいないことはやめて!」と怒鳴られました。聞けばぼくが使っている人間用シャンプーの10倍の値段とのこと。そりゃあ怒鳴られるわな、と項垂れたのでありました。




擬人化とは、愛情を注ぐ対象を得ること。一人暮らしのお婆ちゃんが、庭をイキイキと仕立て、花いっぱいにして暮らしている姿に接する度、賢いなあと、素晴らしい人生を送っているなあと、その方が身に付けた、今日を充実させる知恵に敬服しきり。プレバトの夏井先生はよく「下手な擬人化はしなさんな」と言いますけどね、あれは俳句のテクニック上のお話でありまして、漱石は猫を、寺山修司は競馬馬を、野坂昭如に至ってはこの時期魚沼地方に舞う雪を「掌に受けてやさしき霰かな」と擬人化し、名文・名作を生み出しているではないですか。




宮沢賢治もそうで、小鳥や小動物に物語の材を求め続ける擬人化の執筆人生でありました。素敵ですよねえ、賢治さん。仕事に追われて思考がザラザラしてきたと感じたら、彼が遺した童話をYouTubeで流しつつ設計作業をしています。『よだかの星』『なめとこ山の熊』『注文の多い料理店』、還暦過ぎにもなって、これらの童話が心を均してくれる不思議。思えば賢治さんは、子供向けに書いたわけではなく、一生子供のままだった自分との対話を書き連ねていたんでしょうなあ。いやあそれにしても、美しく清々しい描写です。