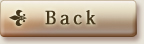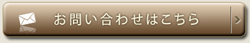耳をすませば
庭と歩調が合う、ことがあります。これだけ毎日何十年も庭庭と言い続け、仕事では庭を思い描いてはその仮想庭を感動の現実庭として出現させることをエンドレス・ラブしているのだから、さぞかし自分ちの庭と足並みが揃っているのだろうと思われるやもしれず、自分でもそれが理想であると意地のように思い込んでいた頃もありました。でも年が明け、そう言えば、レコ大も紅白もパスしちゃったなあと、レコード大賞は誰?紅白のトリは感動的だったんだろうか、サブちゃんは出てないよね、などと思いつつ、今はちょっと違う感慨で庭を見つめていることに気づくのです。歩調が合うことよりも、合わない歩調を意識すること、意識して庭との差を縮め、追いついたら次にはリズムを合わせようとしてみる、その作業が庭を楽しむことなのだと。ひと言で言うなら「同期する」。同期したという結果よりも、同期しようと自分の周波数を庭にチューニングしている時に庭は庭の威力を発揮するのです。

昨年よりも随分と少ないながら、
断続的に咲いては話しかけてくるバラの花。
いい感じ、いい感じ。
ご近所のバラたちも同じく花数は少ない。
不作か?いやいや、この咲き方が普通なのです。
数年ぶりに今年の冬はとても冬らしい冬。
整いました。
昨日も一昨日も、そして今朝もついさっき、以前に庭をやらせていただいたお客様が遊びに来てくださって、そして庭がコロナ禍にあっていかに役立ったかを報告してくれます。それをわざわざ言いに立ち寄ってくれるなんて、ちょっと呆然とするほどうれしいやら、そのうれしさがこうも立て続くとちょっと不思議な気持ちでポッカーンとしている次第。もしかしてだけど、もしかしてだけど、ぼくが思う以上に庭たちは活躍しているのだという実感を、照れながら頂戴し、さてさて次の設計に集中集中。

自分のズレを庭の周波数にチューニングするのと同じく、かつてぼくが夢中で思い描き、実現した庭と同期した人たちによってその世界へ自分の波長が合ってゆく、アフォードされる、何と有難い状態にいるのだろう。

ワルツの状態にある人がやって来たとします。ズンチャッチャ、ズンチャッチャと楽しげに。こちらは無意識にワンツースリー、ワンツースリー、思考が三拍子を刻み出す。やがてピッタリとリズムが重なり意気投合で踊り出す。いい出会いとは調子が合うことに他ならず、それは波動といってもいいし、共通のテンポに乗った時に起こる摩訶不思議なる心の共鳴。それが人を安らがせたり希望の光を照射したりするわけで、逆に波長が合わない場合には出会い頭にトラブル発生、なんてことも起こってしまいます。

霊長類研究の山際壽一氏によれば、これは言葉を使う遥か以前から、人類は音とリズムの交換でコミュニケーションを図ってきたからだそうです。ゴリラならドラミング、オナガザル系だと甲高い声をリズミカルに発して危険を知らせたり、群れの統率を維持する。霊長目ヒト科の生き残りである我々ホモ・サピエンスは、他の猿たちよりも複雑で愛情に満ちた脳機能を有するようになり、その原初的な行動をやがて芸能として、芸術にまで引き上げ音を楽しんでいる。つまり音楽を手に入れたのです。ノー・ミュージック・ノー・ライフは比喩ではなく、遺伝子に則した人間の営み、というわけ。

発達した脳は音楽だけでなく、後には言葉を使うようにまでなりました。ここで重要なのは、言葉を使うずっと前からヒトは音を奏で踊っていたということで、それは言葉よりも深く体に染み込んでいる本能だということ。その潜在的な能力の威力によって、ぼくらは人と対峙した時に耳には聞こえないはずの心のリズムや調べを感じ取り、風景からはこれまた聞き取れない音域の重低音や高音域や、もしかしたら鳥みたいに電磁波のせせらぎまで受信している可能性もある。そうやって音を頼りに暮らしている。しかし誰もそれを意識してはいないわけで、ぼくもそうですけど、ついつい音よりも言葉を重要に捉えてしまって、いやはや、人が抱える多くの苦悩はそれが原因なのです。

庭と歩調を合わせようとすること、庭が発しているリズムを感じ取り音を聞き取り、やがて庭に手招きされて雑草取りや植替えをする、つまり庭のリズムで踊り出します。そのダンスの上達は同じリズムを好むお客様とのセッションにもつながるし、何より自分に高揚感と達成感と安堵感をもたらしてくれるのです。この一連をぼくは『アフォーダンス・ダンス・ダンス』と称して、数日に一度は意識して庭とのダンシングタイムを楽しんでいます。

庭と踊る。ビギンのリズムで、サンバのリズムで、田舎の盆踊りの太鼓だったり、夜ともなればパーシー・フェイス・オーケストラで星空のチークタイム。

ふと、何年か前のNHKの番組から仕入れた知識の引き出しが開きました。前方後円墳、太古のお墓のことが。教科書でお馴染みのあの形を、ぼくらはドローン撮影のように俯瞰して図形で認識するため、え、前方後円墳っていうより、前円後方墳じゃないの?などと、どっちが前でどっちが後ろなのか判然としない。ところが当時の人たちは上空からではなく地平に立って水平にその墓を捉えていたわけで、なぜ方が前なのかというと、手前、方の四角形が建物で、その裏に円形の広場があるというイマジネーションだそうです。四角は祭壇を祀る架空の建造物で、そこに参った後に庭へ行き、アマノウズメ一座のように、AKBのように舞い踊る、なかなか的を射た解釈だと腑に落ちたました。

建物は四角で庭は円形。なぜ庭が円形なのかはそれが人の動きに合致した合理的な形であることと共に、四角い世界から解放され丸い地平と丸い空、当時誰もはっきりとは認識していなかっであろう球状の星に生きているのだという未知にして不思議なパワーを感じる世界観に浸れるから。故にぼくの設計には毎回必ず円形が入っています。

家と庭で家庭。カーテンを開けて、四角い家では感じられない自然の世界観を浴びる丸い庭があれば、太古より受け継がれている知恵に導かれて庭とアフォーダンス・ダンス・ダンス。ホモ・サピエンスは言葉よりも先に音とリズムにアフォードされてきたのだという原点に立ち返れば、雑草取りも芝刈りも水やりも落ち葉掃きもいとをかし。というわけで、さてさて今日の出囃子は、人類発祥の地であるアフリカのサバンナへ思いを馳せてこの曲で。