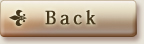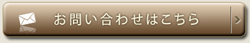コスモスはカオスの対義語
脳は疲れない、とは薬学博士で脳研究者の池谷裕二氏の言葉。アフリカの森にいたリスザルを神の化身にまで昇華させた偉大なるその臓器は、ちょっとやそっとで疲労するなど考えられないほどの容量を有する OS を備えているそうで、よく言われる「人は一生をかけて脳みその数%しか使わない」ということなのでしょう。でも、疲れますよね。設計に行き詰まって、粘って粘ってああでもないこうでもないと無数に存在するアイデアの引き出しを片っぱしから開けて、あの手この手で描き続けているとクタクタになる。慢性的にやりきれない量の設計の山が目の前にあり、それが自重によってガサッと崩れることもある。とにかくもう寝たい、庭でビールを飲んで寝てしまいたいと、そのクタクタは筋肉ではなく確かに脳の疲労であると自覚します。しかし違う、と池谷氏は言います。それは脳ではなく眼精疲労ですよと。


う〜〜〜ん、そう言われればそんな気がしてくる。確かに目が疲れていて老眼鏡にハズキルーペを重ねてもピントが合わなくて、目の裏側に疲労感がある。昼寝をしたり、ゆっくりと湯船に浸かって血行をよくすると頭もスッキリしてまた設計に没頭できるのです。


一応は納得。しかし目の疲れとは違うタイミングで脳機能が低下することもしばしばで、例えば目などほとんど使っていない朝からやる気が出なくて、浮かんできそうになる禁断の言葉、「今日はダメだ」を抑止できないような時。このことについて脳研究者は、「それは脳機能が低下しているのではなくて整理ができていないだけ。配線が絡み合っているか、どこかが外れている、つまりカオスなんですよ」と言います。その混迷状態を知らせる警報の意味で、脳が気分が暗くさせ、やる気を出なくさせるわけで、そのことも含めて正常に機能しているとのこと。そういう憂鬱を解消するためにはいけないお薬がとても効果的だそうで、それを摂取したらたちどころにやる気満々の躁状態になる。そして疲れ知らずで楽しく働いて、やがてオーバーヒートで脳の回線が焼け焦げてしまい、ついに修復不可能になってしまう。


そうか、カオスか。確かに。スケジュール帳に空白が目立つとそうなりやすいし、スケジュール通りに進まなくて適当に文字を入れている時も同じくで、要するに段取り(イマジネーション)の問題なんですよね。カオス、カオス、カオス、カオスとは混迷、混乱のことであり、その言葉の出自はギリシャ語で、天地創造以前の状態を言う。混迷というよりもゼロの世界、意味を持たない世界を指す。カオスの対義語はコスモス。哲学者ピタゴラスは宇宙を秩序ある調和のシステムと捉え、コスモスと名付けました。コスモス、コスモス、コスモス、コスモスとは調和、秩序の意。


秋の野原に調和し秩序だって群生する花を、人々はコスモスと名付けました。カオスからコスモスへ、混沌から調和へ。こじつけにも程がありますけど、だからファインダーでコスモスにピントを合わせていると思考が整うのかもしれません。あ、いや、ほんとにこじつけですけどこれは嘘ではない。やる気が失せたらカメラ担いで花探し、という習慣は正解だったのですね、ピタゴラス様。


コスモスは秋晴れの花。もう暑くないし、半袖では少し冷えるけど寒くはない、そんな日和に揺れている花を目にすると、人は混沌とした心の整理を始める。薄紅のコスモスが秋の日の、何気ない陽だまりに揺れている・・・こんな小春日和の穏やかな日は、あなたの優しさが沁みてくる。明日嫁ぐ私に、苦労はしても笑い話に時が変えるよ、心配いらないと笑った。コスモスの花は今でも咲いていますか。あの日の二人をまだあなたは覚えてますか。・・・右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く中山道、続いてくコスモスの道が。


脳は疲れない。疲れたと思っても、それは目の疲れかイマジネーションの不具合なのだ。そんな時にはカメラ担いで花探し。早い話、秋風に揺れる花を見つめて気分転換し、段取りの整理整頓をしなさいってことです。
なぜコスモスは群生するのかといえば、身を寄せ合い、互いが支え合うことで倒れないように、という天与のシステム。
か細い茎で秋空に向かって咲き競う花、いいんだなあコスモス。
さ、今日の設計のポイントは「狭い庭を有効に使うアイデア」「植物に囲まれて過ごす庭」「リビングからの風景を描く」。この3点を点々繋がり線となすことに集中いたします。
お、いいぞいいぞ、こうして進行方向を言葉にすることで、スリープ状態だった OS が起動する。