亡くなられた後、奥様としては、その庭をどうにかしたいと思いつつも「お父さんが楽しんでいた庭だから」と、どこまで手をかけていいのか迷い、造園業者に相談して、植物を少しだけ整理して家側に砂利のスペースを確保したのだそうです。これです。


ただ、その気持はまだ何となくで、それ以上にはふくらまなかったようです。「何となく」のまま。亡くなった家族の遺品を整理するのってむずかしいですよね。何年経ってもそのままというお宅もあります。わかりますよねその気持。この庭はお父様の遺品みたいなものなのです。
数ヶ月が過ぎて、奥様の気持の中からその「何となく」は消えませんでした。
これなんですよこれ!消えることのない「何となく」。
ぼくはこの感じがとても好きです。消えない「何となく」が、実はぼくにとってとても大事な感覚なのです。
書店に並んでいる夢実現のテキスト(自己啓発の本とか)には、「ぼくは将来プロゴルファーになる」、「5年後までに家を建てる」、そういうはっきりとした目標を掲げて、そこに至る計画を立てて、真っすぐにその目標に向かっていくということが重要であると書いてありますよね。渡邉美樹さんの「夢に日付を」とか。
ぼくはそれに、ちょっとだけ違和感があります。美樹さんは大尊敬していますけど、ぼくはもっと行き当たりばったりでもいいんじゃないかなあって。その方がぼくにはエキサイティングに感じるのです。
ぼくの座右の銘は「すべてなりゆき」です、なんて、半分ふざけて言っていた時期がありました。でもそれって、けっこう大まじめにそう思っていることなんですね。大好きなエルビス・プレスリーも、ジョン・レノンも、今大人気の坂本龍馬も、なりゆきの人生ですからね。自分に正直に、自分らしく行きているうちに時代に引っ張り上げられて、本人も思ってもいなかったような大きな事を成すような、そういう人生です。そういうのがいいんです。
ただし、これはぼくなりの大発見だったんですけど、そうやってなりゆきで生きて、しかもエキサイティングに楽しく充実して生きるためには、コツがあります。
「何となく」を、やわらかく思い続けること。
これまでこのコツで、ずいぶんといろんなことが実現しました。握りこぶしで「◯◯するぞ!」じゃなくて、やわらかく思い続けていたことが、気がついたらすでに実現していたという経験です。仕事も、店も、家も、妻と子供たちも。身の回りのすべてがその「何となく」によって実現したのです。楽しいんですよこれって。「何となく」を、やわらかく思い続けること。
この「何となく力」については、長くなるのでまた今度にして。
奥様の中の消えない「何となく」を感じた時点で、ぼくは「いい庭ができる」と確信しました。その「何となく」と、ぼくが大事にしている「何となく」とが感じが似ていたからです。
明日、ぼくが奥様に提案したプランをご覧いただきます。
そういえば、庭を設計すること自体「何となく」をカタチにする作業なんですよね。だから得意分野なのです。ぼくは「何となく」を実現させるスペシャリスト。
こうして来る日も来る日も庭を設計している今の仕事も、小学校の卒業文集に「将来、絵を描いて暮らしていく人になりたい」と書いた、その「何となく」が消えなかった結果なんだと思います。
「何となく」をやわらかく思い続けることで、人生は思い通りになる、・・・かもしれないなあって、やわらかくそう思い続けています。












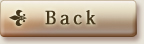
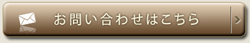










 After 1
After 1


 After 3
After 3
 After 4
After 4
 After 5
After 5
 After 6
After 6
 After 7
After 7
 After 8
After 8




















































































































